今回は、前回から引き続きの内容になります。
前回はこちらから
ということで、改めて今回は【家庭】について深掘りしていきます。
※家庭についてですが、これは親(保護者)と学校(教師)の両方の立場から見たモノを、総合的および実体験から基づいてまとめています。
発達障害の特性をもつ子の子育て環境に問題がある家がとても多いという問題です。つまり、発達障害の特性をもつまたは、類似する言動をとる子を良くするも悪くするもすべて親(保護者)にあるということです。と言ってもおかしくないと思っています。
その子をどのように育てるかは親(保護者)で決まると言っても過言ではありません。
では、どうしてそう思うようになったのか?

現実と家庭についてまとめていきたいと思います。
昨今、家庭環境については様々な状況があります。特に親(保護者)で大きく異なります。
1 両親のどちらかが働き、どちらかが家で育児家事などを行う
2 両親の共働き
3 片親で働き
4 祖父母等と同居
5 4で1の場合
6 4で2の場合
7 4で3の場合
8 その他・・・
と、簡単にまとめただけでもこれだけの家庭状況があります。
何が言いたいのかと言えば、これだけ千差万別な家庭環境でさらに、分けられるところがあります。
まず、改めて発達障害についてこちらでまとめています。ぜひ、読んでください。
目次
簡単な良し悪しだけで考える
まず、発達障害の特性または類似する言動があるモノをもつ子に対して、保護者が良くするも悪くするもすべてあるという言い方をしましたが、少しオーバーに言いました。
というのも、基本的に子どもと関わる時間が一番長いのが【親】です。
正直、どのような状況であれ、できるだけ一番長くないと良くないのです。
子どもが頼るのは【親】なのですから・・・
つまり、簡単な良し悪しだけでいえばどれだけ、子をわかって上がられるかにかかってきます。
子どもの特性を受け入れられるかられないか
これまで、様々な人を見てきました。
これは、発達障害の有無だけではありません。
どういうことかというと、
受け入れられる場合は、早期に子の特性を認め適切な支援を求めます。
そして、行動に移すことで子に対して適切な支援を導入し成長を助けます。
しかし、受け入れられなければどうでしょうか?
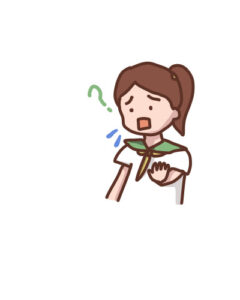
例えば・・・
発達障害という特性をもっていたとします。
それを、受け入れられない親がいます。
その親は、子どもが発達障害と認めず適切な支援を入れることもありません。
やがて、問題行動を繰り返すまたは、周囲についていくことができず
孤立し引きこもりや問題行動がさらに発展してしまい犯罪行為に繋がっていく
事が考えられます。
※すべてではありません
わが子の特性を受け入れるか受けいらないかで、子どものその先が大きく変わります。
この受け入れることが難しい親が、発達障害の子を育てる状況の問題を著しく困難にさせている原因にあります。
学校での問題
前回の記事で、学校についてまとめました。
前回の記事はこちらから
何より、【連携】が大切ということを書きましたが、この特性を受け入れることが難しい親はその【連携】のを作ることが出来ません・・・

まぁ、それはそうなんです。学校側が支援が必要と言っても、「うちの子をバカ扱いするのか」と話も聞かずキレ散らかす親もいます。
これは、子どもをめぐる状況だけではなく、高齢者介護でも見られます。
なので、これは特別な事ではありません。
特別でないから、問題でもあります。
これが、学校側が支援をしようと思ってもできない。その児童に手を取られてしまい他の児童に手が回らなくなってしまう要因の一つでもあります。
この問題が、クリアされると全体の大きな一歩になると思っています。
と、この問題ばかりになってしまいましたが、それだけではありません。
子の特性を受け入れたものの・・・
子の特性を受け入れたものの困ったことがあります。

発達障害は、知的障害や身体障害ではありません。
ですので、場所によっては公的機関を利用しづらいことがあります。
どういうことかというと、
発達障害には、特性の中にコミュニケーションが取りづらい、他人を殴ったりする他害行動があったり等の問題行動があります。
そうする、通常の学童を利用すると問題行動が目立ってしまうことで居づらくなるなどがあり、放課後等デイサービスを利用すると、知的レベルが合わずこれはこれでコミュニケーションが取れず問題行動をとってしまうなどの悪循環があります。
その為、居場所がなくなったり親としてもどうしていいかわからなくなってしまう問題があります。
そして、同居する祖父母からの理解が得られないという問題もあります。
発達障害は、近年表に出てくるようになりました。そのため数十年前まで認知されていなかったので、祖父母世代が理解することが難しいこともあります。
そのことから、親が悩んでしまう場合も多いです。想像以上に!!
しかし、その逆もあります。特性を祖父母が心配しても親が受け入れないという場合もあります。これも以外に多い・・・
さらに、悪い環境があります。親友からの理解が得られない・・・
発達障害も本当に様々です。軽い重いや手が掛かる掛からない、他害の有無等々様々です。
親友に相談しても、そっちは良いよねウチは全然できないから大変なんだけど。
と、謎の程度自慢が始まるのです。
このように、特性を受け入れても親(保護者)には、様々な問題が本当に多いです。
そして、この先どうすればいいのかという不安が常に付きまといます。
と、いうことで今回は【家庭】側から書いてみました。
まとめ
これまでの【家庭】側についてまとめると
・家庭環境
・大人の誤った発達障害への理解
・大人同士の子どもへの認知の不一致
・子の発達障害に対しての不安
と少し深掘りするだけでもいろいろな課題が見えてきました。
この中で特に、大人の誤った発達障害への理解や発達障害への拒否反応を見せる親・保護者に対してのアプローチで悩まれる、親友や教師が多くいました。
そして、不安についても多く上げる親・保護者の方も多くいました。
今後、どのようにこの課題を解決していくか、色々な方と相談しながら進めていきたいと思います。
課題についてもどのように進めていくか、当ブログで書いていきます。
ということで、今回はここまでとさせていただきます。
次回は【周囲の環境】について書いていきたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。






コメント