前回までの話はこちらから読んでください。
会議で決まった事はこちらから
学校に少しづつ行けるようになったいっち。
前回は、学校に行く行かないからの始まりでした。
今回は、学校の過ごし方について話をしていきたいと思います。
基本的に、通常学級の教室とは別の教室でいっちのスペースを作って対応することになりました。
登校するとまず、そのいっちのスペースに行きます。
授業には着いていけていないため、独自の時間割で行動します。
授業時間は他児と一緒。
休み時間は、教室に行き友達と過ごし授業が始まるといっちスペースへ戻るということです。
授業時間のいっちの学習内容は、主に簡単なプリント学習を行いました。疲れるとアイロンビーズで作品をいろいろと作っていました。

これは一部ですが、このような感じで少しづつ毎日作っていました。
片もいろいろあってネットにも展開されているそうです。
その他には、先生と学習用のボードゲームをするなどをして過ごしていました。
ボードゲーム
言葉のパズル もじぴったん
まちころ
将棋などもやっていたそうです。
クラスの授業では、参加できそうな理科や家庭科の授業はいっちのペースで参加していました。
学習プリントは、学習障害の特性があるため小学校1年生のプリントから始めています。
基本的には、手の空いている先生が適宜付き添って対応している様子でした。
メンタル面で学校に居る事が辛くなったら、親を呼び親と一緒に下校するという対応を取りました。
これを1年続けたころから、学校を休むことは減り(主に月曜日や連休翌日は休む傾向にあり)コンスタントに学校に行くようになりました。
しかし、クラスメイトの一部の児童やクラス外の児童から当然狡い等の話があったようですが、適宜先生方が対応してくださったとのことです。
基本的に学校の支援方法については、親からは言うこともありませんでした。
対応してくださることに感謝でした。
会議から実対応に至るまで、校長先生をはじめとした先生方の理解を頂けたことがとても大きいと思っています。
今でも、子のいっちのような対応をされている学校を聞いたことがありません。それどころか、耳を疑うようなことも聞きました。
そして、合理的配慮が広がる中でもこのような対応をできる事が当たり前になることも現状ではこの先もないと思っています。
このあたりの事については、改めて記事にしていきたいと思います。
次回は、子供たちの障害者手帳の取得を目指していきます。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
アイロンビーズのサイト






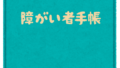
コメント